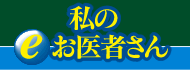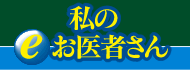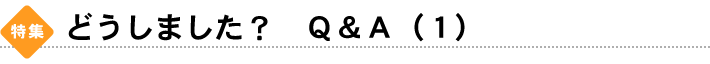|
昼のあいだ、目の前に「糸くずのようなもの」が絶えず見えています。夜のあいだや、昼でも日陰では見えません。このような症状が出るのはどういった病気なのか、治療法などはあるのか教えて下さい。痛みはありません。なお、以前眼科医から、この症状について「後頭部の視神経を圧迫しているのではないか」と言われ、MRIで検査しましたが、「脳動脈硬化の一歩手前だが治療の必要はない」との結果でした。
(71歳/男性/会社員)
A)加齢のための硝子体剥離で心配ありません。
このような症状を医学的に「飛蚊症」と呼んでいます。この濁りには、生理的なものと、病的な原因によるものがあります。
1)母体内で胎児がつくられる途中では、硝子体に血管が通っていますが、眼球が完成する時になくなっていくのが普通です。しかし、生まれた後も血管の名残が硝子体に残存し、「濁り」となることがあります。この飛蚊症は、若年者に多く、生理的なもので健康な目にも起こるものですから、症状が進まない限りはあまり気にしなくても大丈夫です。
2)年をとると硝子体はゼリー状から液体状に変化し、硝子体は次第に収縮して網膜から剥がれます(硝子体剥離)。急に丸い輪や、Cのような形の飛蚊症が現れますが、生理的な現象です。また、若い人でも、強度の近視の場合にはこの硝子体剥離が早期に起こります。出始めは濃く気になりますが、半年くらいたつと次第にうすくなっていきます。
3)飛蚊症を初期状態とする病気は、網膜剥離、網膜裂孔、硝子体出血、眼底出血、ぶどう膜炎などがあります。見える飛蚊症の数が桁違いに増えたり、形が変わったり、視力が落ちるなどの急な変化があったら、必ず眼科医を受診してください。
質問の方は、おそらく2番目の硝子体剥離と思われますが、心配はないと思います。
飛蚊症のほとんどが病気ではないものですが、ときに思いがけない病気が原因となっていることがあります。症状を感じたら早めに眼科で検査を受け、医師の指示に従ってください。早期発見、早期治療があなたの目を守ります。
|